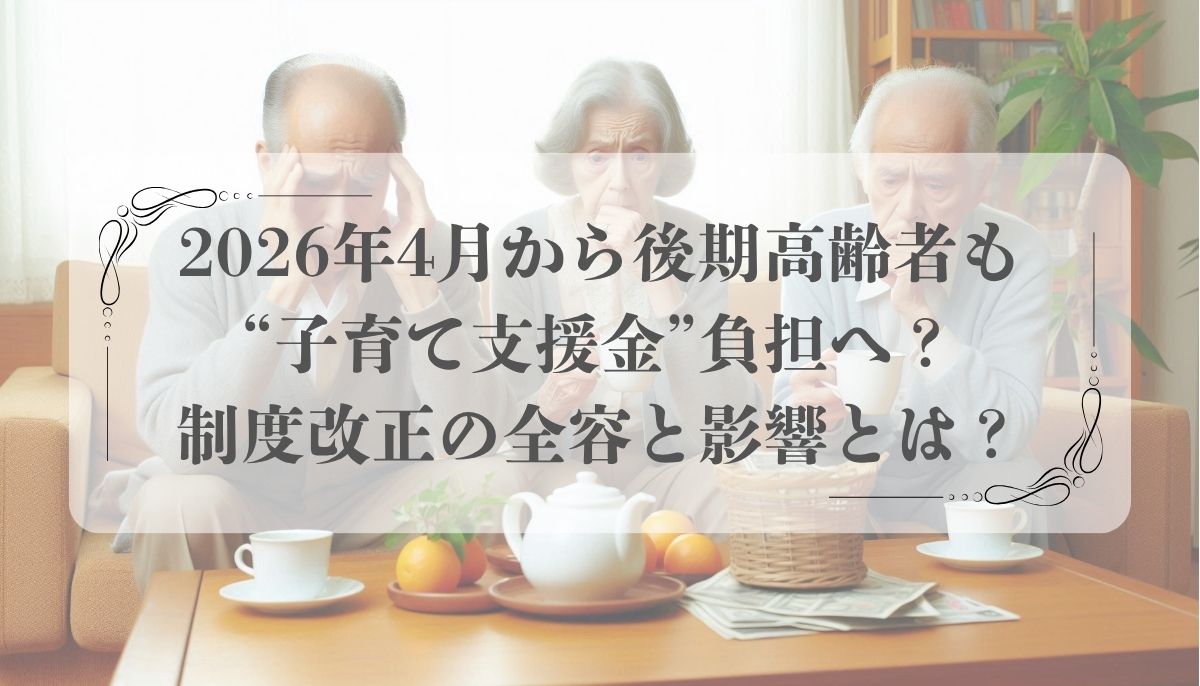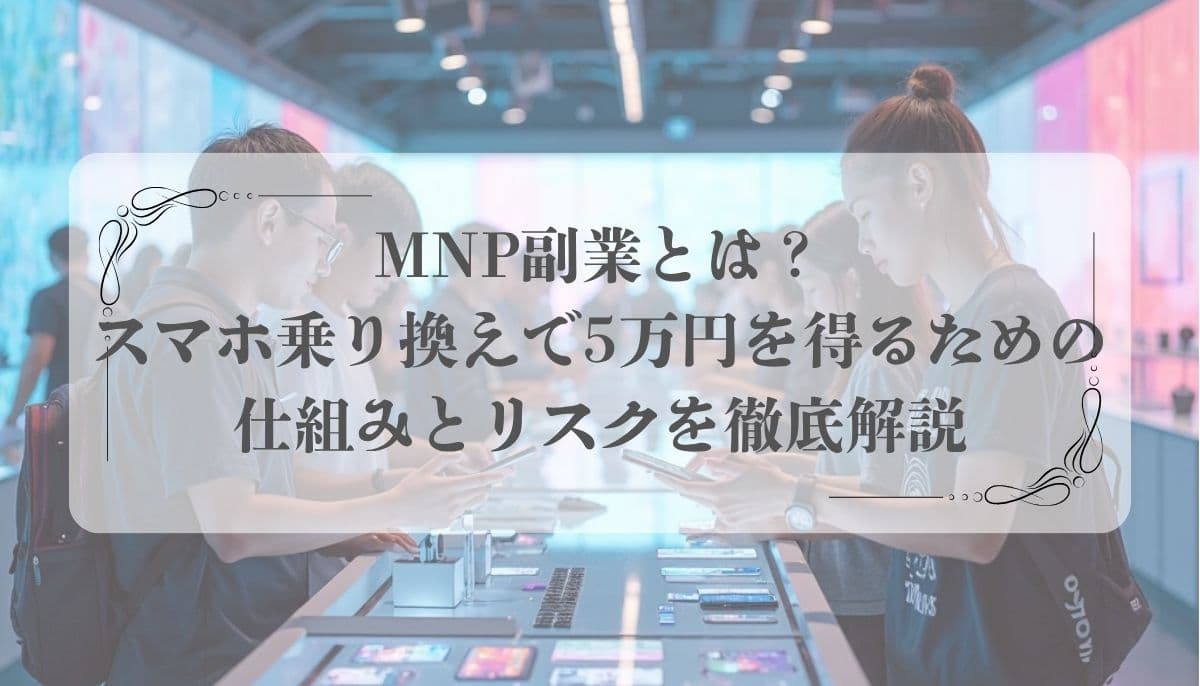ブログにご訪問いただき、ありがとうございます。尾﨑まり江です。初めましての方はプロフィールもご覧ください。オンラインビジネス、美容、副業について発信しています。
この記事がおすすめな人
2026年4月より新たにスタートする「子ども・子育て支援金制度」。これまで現役世代が主に担っていた子育て支援の費用負担が、今後は75歳以上の後期高齢者にも一部求められる見通しです。
「年金だけで暮らしているのに、また負担が増えるのか?」と不安に思われる方も少なくないでしょう。
この記事では、この制度改正の背景、具体的な負担額の目安、対象者、そして私たちが今できる備えについて、わかりやすく解説していきます。
子ども・子育て支援金制度とは?
「子ども・子育て支援金」とは、政府が2026年4月から開始予定の新しい少子化対策財源制度です。これは、子育て支援に必要な費用を社会全体で分担するため、医療保険料に上乗せする形で徴収されるものです。
この支援金は以下のような事業に使われます。
- 出産・育児一時金の充実
- 保育園・こども園の整備
- 学童保育の支援
- 児童手当制度の拡充
つまり、単なる税金ではなく、将来の日本を支える子どもたちへの直接的な支援となる目的があるのです。
なぜ後期高齢者も負担対象になるのか?
これまで子育て支援の費用は、主に現役世代(会社員や自営業者)が負担していました。しかし、急激な少子高齢化により、現役世代への負担が重くなり、制度の持続可能性が危ぶまれるようになりました。
そのため政府は、「全世代型社会保障」の理念のもと、高齢者も含めた広い世代での負担分担へと制度設計を見直したのです。
後期高齢者の具体的な負担額は?
では、実際に後期高齢者がどれほどの金額を負担することになるのでしょうか。2025年時点の政府試算によると、支援金の徴収は年収や所得に応じて段階的に行われます。
▼ モデルケース例
| 年金収入 | 支援金年間負担額(見込み) |
|---|---|
| 180万円 | 約1,200円 |
| 250万円 | 約2,500円 |
| 350万円 | 約4,000円 |
つまり、月額でいうと100円〜300円程度の負担増と見られています。ただし、低所得者層への配慮措置も設けられる予定です。
影響を受けるのはどんな人?
この支援金の徴収対象となるのは、次の条件を満たす方です。
- 75歳以上で後期高齢者医療制度の加入者
- 所得が一定以上の方(住民税課税対象者など)
非課税世帯や一定の収入未満の人については、支援金負担が免除または軽減される可能性があります。具体的な基準は、今後自治体や保険者からの案内で明らかになる予定です。
制度改正のメリットと課題
メリット
課題
世代間の理解を深めるために
「なぜ子どもがいない高齢者も負担するのか?」という疑問の声も当然あります。しかし、この制度は未来の日本社会を支える子どもたちを守るためのものであり、自分の孫やひ孫、地域社会全体の未来への投資とも言えます。
すでに多くの高齢者が地域の子育て支援や見守り活動に積極的に参加している現状を踏まえれば、「金銭面での支援」もその延長線上にあるのかもしれません。
まとめ:慌てず正確な情報収集を
今回の制度改正により、後期高齢者にも一定の負担が発生しますが、その金額は限定的で、生活を圧迫するレベルではないと見られています。
とはいえ、各保険者によって案内方法や詳細が異なるため、必ず地域の窓口や公式資料を確認するようにしましょう。
\今からでも収入の柱を/
外にお勤めに出るのは難しいという後期高齢者。少しでも負担を減らしたい、まだ元気なのでパソコンを使って収入を得たい、という方は以下のボタンをクリックして詳細をご覧ください。
今後も最新情報をチェックして、安心して暮らせる毎日を目指しましょう。